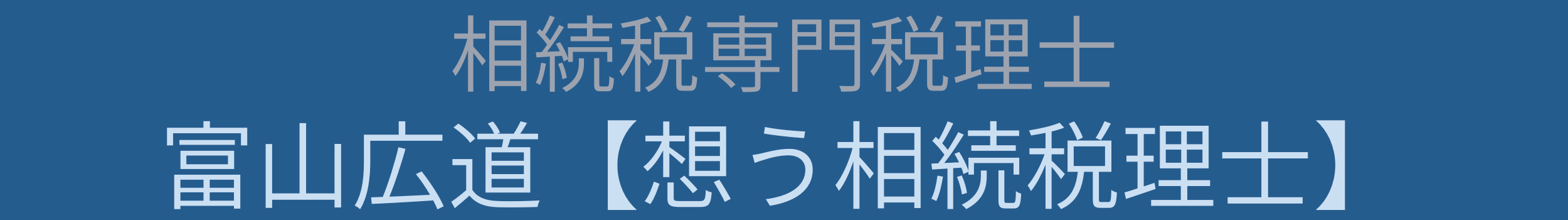相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が会社に貸していたお金(貸付金債権)について、「債務免除したので、もう存在しない」ということで相続税申告において財産計上しなくてよいのか、また仮に存在するとして、回収が難しそうな場合に「相続税評価を下げられるのか」が問題になった判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z268-13197)(一部抜粋加工)
平成30年9月27日判決
貸付金債権は存在する?
相続税は、相続開始時点に亡くなった方がどのような財産を持っていたかを基準に計算します。
そのため、預貯金や不動産のように分かりやすい財産だけでなく、会社に対する「貸付金」や「未収入金」のような「見えにくい財産」も対象になり得ます。
本件では、亡くなった方が(さらにその配偶者からの相続を経て)会社に対する貸付金債権を有していた点が問題になりました。
納税者側は、「会社に対して債務免除の意思表示があったので、貸付金債権は存在しない」と主張しました。
しかし、裁判所は、そのような意思表示があったとは認められない、という事実認定を前提に、債権は存在すると判断し、更正処分を適法としました。
ここで重要なのは、債務免除は「気持ち」や「雰囲気」では成立しにくい、という実務感覚です。
特に相続税の場面では、「本当に免除したのか」「いつ、誰が、どの範囲で免除したのか」を裏付ける事情が問われやすく、口頭のやり取りだけでは争いになりやすい傾向があります。
また、会社側の会計処理(貸付金残高の計上など)も、債権の存否を考える上で無視できない材料になります。
本件でも、会社が債権の存在を前提に処理していた点などが、判断に影響し得る事情として扱われています。
貸付金債権の評価は原則「元本+利息」(例外は限定的)
次の論点は、仮に貸付金債権が存在するとして、その金額をどう評価するかです。
相続税では、財産は原則として「時価」で評価します。
もっとも、貸付金債権は市場で日々売買されるような財産ではなく、交換価値が外から見えにくい性質があります。
そのため、実務上は財産評価基本通達に沿って評価することが基本になります。
本件では、財産評価基本通達204(原則)により「元本の金額と既経過利息との合計額」で評価することが基本とされました。
納税者側は、「回収が困難なのだから、財産評価基本通達205(例外)を広く解して減額すべきだ」という方向の主張も行っています。
しかし裁判所は、画一的な評価方法を採用すること自体の合理性(公平・便宜・徴税コスト)を述べつつ、例外である財産評価基本通達205の適用場面は限定的だ、という考え方を示しています。
つまり、「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」は、相当程度「客観的に明白」な状態が求められ、単に「業績が厳しい」「資金繰りが大変そう」という感覚だけでは足りない、という整理です。
「どうせ回収できないだろう」と思ってゼロ評価や大幅減額で申告すると、後から否認されやすく、追徴や加算税のリスクが高まります。
逆に、例外適用を狙うなら、通達が想定するような客観状況に近い事実関係と、資料の積み上げが必要になります。
相続が近い方に確認していただきたい実務上の留意点
今回の判決事例から、相続が近いご家庭が学べる実務上の注意点は大きく3つあります。
1つ目は、「会社への貸付金」は、相続財産として見落としやすい一方で、争点になりやすい財産だということです。
親族経営の会社では、資金繰り支援や立替の延長で貸付金が積み上がっていることが少なくありません。
そして、その「曖昧さ」が、相続税申告時に火種になります。
2つ目は、「免除したつもり」「返さなくていいと言ったはず」という話は、相続税の世界では通りにくいことがある、という点です。
免除を主張するなら、いつ、どの範囲で、どのように意思表示したのかが分かる事情が必要になります。
少なくとも、後から説明可能な形で整理しておかないと、税務調査や争訟の局面で苦しくなります。
3つ目は、「回収が難しい=すぐ減額できる」ではない、という点です。
財産評価基本通達205の適用は例外であり、客観的に明白な事情が求められる、という方向性が示されています。
したがって、安易なゼロ評価や大幅減額は避け、状況に応じて、資料の収集・評価方針の検討を行うことが重要です。
特に、相続税は申告期限があり、後から慌てて証拠を集めようとしても間に合わないことが多いです。
早めの検討が重要です。
 想う相続税理士
想う相続税理士
「免除したつもり」「回収できないはず」といった感覚だけで申告方針を決めるのではなく、相続開始時点の事実関係と資料を踏まえて、通達上の原則・例外のどこに当てはまるのかを丁寧に検討することが、結果としてリスクを最小化します。