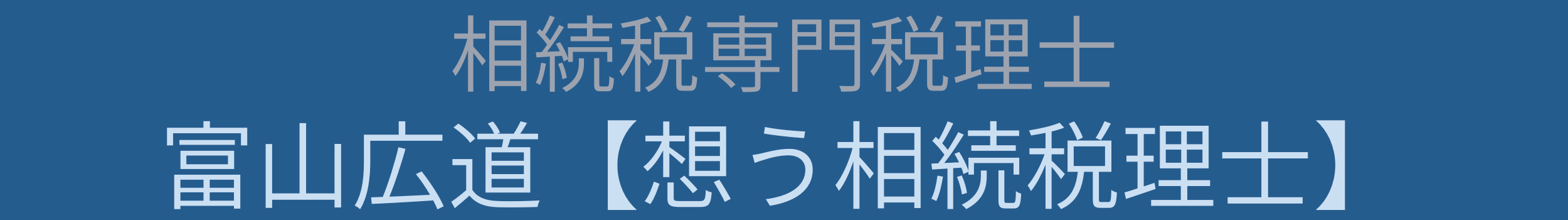相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続後に事業用建物を建替えている途中でも、小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)が検討できる場合と、面積・範囲判定の落とし穴について、お話します。
申告期限に(まで)「事業で使っている」要件(事業継続要件)がある
小規模宅地等の特例は、土地の評価を大きく下げられる反面、要件が細かい制度です。
特に、亡くなった方が使っていた店舗や工場などの「事業用の土地」は、相続人側がその事業を引き継いで、一定期間(通常は申告期限まで)きちんと事業を続けていることが前提になります。
ここで悩ましいのが「申告期限の時点で、土地が事業の用に供されているか」です。
店舗が老朽化していて、相続後すぐに建替えを始めた場合、申告期限の時点では「建物が完成していない(工事中)」ということが起こります。
すると形式的には「今は営業していない」「建物がない・使っていない」と見られやすく、特例がダメなのではないか、と不安になります。
実務でも、この「見た目」が原因で、最初から特例を諦めてしまうケースがあります。
しかし、建替えは事業継続のために必要な更新です。
そのため、一定の条件を満たすなら、工事中でも「事業の用に供している」と扱う考え方が用意されています。
建替え工事中でも「事業用」とみなす発想(ポイントは着工)
結論から言うと、申告期限までに建替え工事に着手しているのであれば、申告期限の時点で工事中でも、事業用宅地としての特例を検討できる場合があります。
ここでのキーワードは「完成」ではなく「着手(着工)」です。
申告期限までに、相続人が事業を引き継ぐ意思と実体をもって動いており、その一環として建替えに入っているなら、申告期限に「たまたま」工事中であることだけを理由に、直ちに排除するのはバランスを欠く、という整理です。
ただし、何でもOKという話ではありません。
たとえば、次のような点は、税務上の説明材料として重要になります。
申告期限までに、事業の継続(再開)に向けた動きがあること(準備・契約・届出など)
建替えが「事業のための更新」であること(単なる更地化や転用のためではないこと)
申告期限までに、建替え工事へ実際に着手していること(契約日だけでなく、着工の客観資料)
特に、着工時期は争点になりやすいので、工事請負契約書、工程表、着工届、写真、支払記録など、後から説明できる形で整理しておくのが安全です。
要注意:建替え前後で「事業に使う部分」が変わると、適用面積が削られる
もう一つ、見落とされがちなのが、「特例の対象となる土地の『範囲』」です。
建替えの前後で、店舗の配置や駐車場の取り方が変わり、敷地のうち「事業に使っている部分」が増えたり減ったりすることがあります。
このときの考え方はシンプルで、実務的には、「建替え前と建替え後を比べて、事業に使う部分が小さい方(より狭い方)を上限にして、対象範囲を考える」という取扱いになるものと思われます。
具体的には、
逆に、建替え後に事業で使う部分が大きくなったとしても、建替え前に事業で使っていた範囲を超えて増えた分まで自動的に広がる訳ではない
要するに、建替えをきっかけに対象面積を広げようとすると、説明が難しくなりやすい、ということです。
また、土地全体が一体に見えても、実際には「事業エリア」と「それ以外(私的利用・遊休・別用途)」が混在していることがあります。
この切り分けが甘いと、特例の適用面積を否認されたり、調査時に長期戦になったりします。
したがって、建替えのタイミングでは、次のような整理をおすすめします。
建替え後:どの部分を事業に使う予定か(完成後の図面・駐車場計画)
共通:申告期限時点で「事業継続のためにその土地を使っている」と言える根拠(着工資料・準備資料)
「工事中だからダメ」ではなく、工事中でも制度が想定しているケースかどうかを、時系列と資料で組み立てるのがポイントです。
不安がある場合は、申告書を出す前に、特例の前提となる事実関係(着工日、事業継続の実体、事業用部分の範囲)を、専門家と一緒に点検しておくと安心です。
 想う相続税理士
想う相続税理士
大切なのは、完成の有無ではなく、申告期限までに事業承継としての実体があり、建替えに着手していることを客観資料で示せるか、そして建替え前後で事業用部分の範囲を慎重に整理できているか、です。
制度の趣旨に沿う形で、事実関係と証拠を丁寧に整えることが、結果的に相続税のリスクを下げる近道になります。