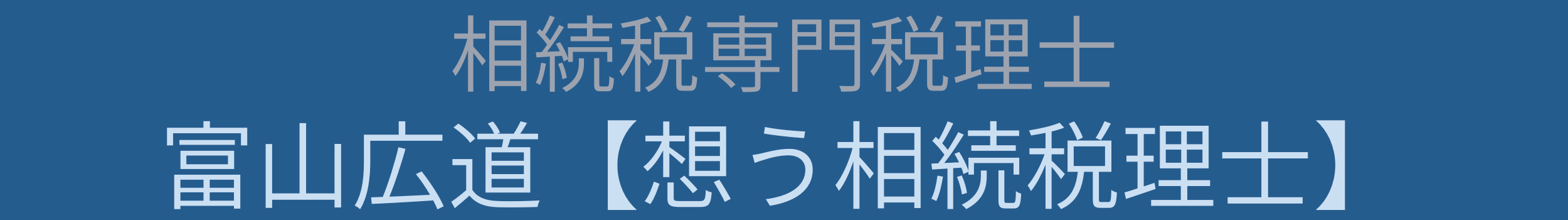相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続開始時点で未収だった事業用定期借地権の預り敷金が争点となった裁決事例について、お話します。
出典:TAINS(F0-3-159)(一部抜粋加工)
平18-01-31裁決
事業用定期借地権と敷金
事案の舞台は、アミューズメント施設のための事業用定期借地権が設定された土地です。
借地契約にあたり、借主から貸主へ多額の敷金が預けられる形になっていました。
この敷金は、契約終了時まで無利息で預けっぱなしにしておき、契約が終わったときにまとめて返す、という条件になっています。
裁決書では、まず事案の概要を次のように説明しています。
本件は、事業用定期借地権が設定された土地に係る敷金の一部が相続開始時において未収となっている場合、相続財産に計上した当該未収敷金に係る返還債務を債務控除の対象とする際に、当該未収敷金の全額を債務控除できるか否かが争われた事案である。
ポイントは2つです。
1つ目は、「敷金の一部をまだ預かっていない(未収)の状態で相続が始まった」という点です。
2つ目は、その未収預り敷金に対応する「将来の返還義務」を、相続税でどこまで債務控除できるのか、という点です。
相続税の申告では、亡くなった方が生前に負っていた債務は、一定の要件を満たせば、遺産から差し引くことが認められています。
預り敷金の返還義務も、基本的には「将来返さなければならないお金」ですから、債務控除の対象となり得ます。
納税者側と税務署側の主張の違い
この裁決では、相続人側と税務署側で、考え方が大きく分かれました。
まず、相続人側(納税者側)は、未収預り敷金について「そもそもまだ預かっていないのだから、預託は成立しておらず、経済的利益も生じていない」と主張しました。
財産評価基本通達27-3(2)には、定期借地権の評価にあたり、「保証金、敷金など」「の預託があった場合」の経済的利益の計算方法が定められています。
そこで納税者側は、「未収の敷金は『預託があった場合』には含まれないのだから、ここでいう経済的利益を持ち出して、未収預り敷金の返還債務を割り引くのはおかしい」と主張した訳です。
一方で、税務署側は、相続税法第13・14・22条の考え方から、「債務控除する金額は、その債務の『現時点の経済的価値』で評価すべきだ」と整理しました。
長期・無利息で預かっている金銭債務の場合、貸主側には「通常なら受け取れたはずの利息相当額」を、契約期間中ずっと享受できることになります。
そのため、税務署側は「その利息相当の経済的利益の現在価値分だけ、債務の額は実質的に軽くなっているはずだ」と考えました。
裁決書でも、次のように整理されています。
本件敷金は、本件契約が終了するまで賃貸人において返還を要しない無利息のものであることから、本件敷金に係る返還債務の額は、通常の利率と本件相続開始日から本件返還期日までの期間から求められる複利現価率を用いて本件相続開始日現在の経済的利益の額を計算し、本件敷金からこの経済的利益の額を控除した金額とするのが相当である。
つまり、形式的に見れば「返すべき金額=敷金全額」であっても、相続税で債務控除できる額は、「経済的利益(利息相当分)を差し引いた後の金額」と考えるのが妥当だ、と判断されたのです。
また、未収敷金そのものについても、「契約で支払義務が確定している無利息の金銭債権」であることから、相続時点から支払期日までの期間について利率を用いて割り引き、現在価値で評価すべきだとされました。
裁決の結論と実務上のポイント
この裁決では、まず、敷金の返還債務自体は「相続開始時点で既に確定している債務」であり、相続税法第13・14条に定める債務控除の対象になることが確認されました。
その上で、長期無利息の敷金については、「将来の返還額そのまま」ではなく、「相続開始時点の経済的価値」に引き直して債務控除額を計算すべきだと判断されています。
また、未収敷金は、相続財産として未収入金に計上しつつ、その評価額も現在価値に引き直す、という整理がなされています。
結果として、当初の更正処分の一部は取り消されましたが、「敷金は全額そのまま債務控除でよい」という納税者側の主張が全面的に認められたわけではありません。
 想う相続税理士
想う相続税理士