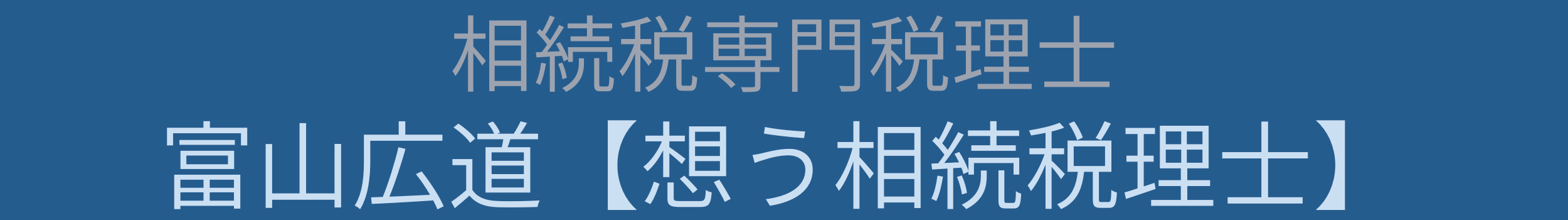相続税専門税理士の富山です。
今回は、「土地評価における『特別の事情』の有無」と「名義書換がされていない非上場株式を配当還元方式で評価できるか」が争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z270-13385)(一部抜粋加工)
令和2年2月25日判決
処分禁止の仮処分登記付土地・名義書換未了株式
相続税は、亡くなった時点の財産の「時価」を基準に計算します。
ただし、実務では、原則として財産評価基本通達(評価通達)という全国一律のルールに従って評価します。
しかし、評価通達に基づいて算定した金額が、常に「時価」と一致するのでしょうか?
本件では、まさにその点が正面から争われました。
第1の争点は、当該土地に処分禁止の仮処分登記が付されていたことから、「評価通達どおりに評価すると、実際の価値より過大になるのではないか?」という主張がなされた点です。
納税者側は、所有権の帰属が争われ、処分禁止の仮処分がある土地は、買主が安心して買えず、交換価値が下がるはずだと主張しました。
第2の争点は、名義書換がされていない取引相場のない株式(非上場株式)について、「議決権を行使できないのだから、支配力は小さい、したがって、配当還元方式が使えるのではないか?」という主張がなされた点です。
評価通達では、一定の少数株主などに該当する場合に配当還元方式が適用されますが、その入口である「議決権割合」の見方が問題になったのです。
「特別の事情」がある?
まず最初に土地です。
裁判所は、評価通達の評価方法(本件では路線価方式)が一般的に合理的であることを前提に、評価通達による評価額は原則として時価を上回らないと推認できる、という判断枠組みを示しました。
その上で、通達評価を外すには、「その評価方法では適正な時価を算定できない特別の事情」が必要だ、と整理しています。
納税者側が持ち出したのは、処分禁止の仮処分登記です。
一般の方の感覚でも、「売れない(売りにくい)土地なら安くなるのでは?」と思いやすいところです。
しかし、裁判所は、処分禁止の仮処分が付いていること自体から、直ちに「特別の事情」があるとは言えない、という方向で判断しました。
理由の骨子は、仮処分は事情変更等により取消しの申立てが可能であり、相続開始日以前に、本件土地贈与を認める高裁判決が存在していたため、取消しが認められる蓋然性が相当程度高かった、という点です。
つまり、「仮処分がある=交換価値が大きく毀損している」とまでは評価できない、ということです。
本文でも、次のように述べています。
以上からすれば、本件相続開始日において本件土地につき処分禁止の仮処分がなされていたことは、本件土地の客観的交換価値を評価するに当たり、評価通達に定める評価方法により難い特別の事情に当たるとはいえない。
登記簿謄本に何らかの「制限」っぽいものが付いているからといって、安易に減額評価に飛びつくのは危険です。
その制限が、いつまで、どの程度、現実の売買を妨げるのかを、手続面も含めて立証する必要があります。
「買主が嫌がるはず」という一般論だけでは足りず、取消し可能性、紛争の見通し、実務上の取引阻害の程度まで踏み込んで問われる、というイメージです。
名義書換未了でも議決権は「あり」
次に株式です。
本件の株式は「取引相場のない株式」で、会社規模は「大会社」に該当すると認定されています。
大会社の非上場株式は、原則として類似業種比準方式(または選択により純資産価額方式)で評価します。
一方、一定の少数株主等に当たる場合は、例外として配当還元方式が適用され得ます。
そこで、納税者側は、贈与で取得した株式について会社が名義書換を拒んでいた期間があり、その間は議決権を行使できなかったのだから、議決権割合は5%未満として配当還元方式にすべきだ、と主張しました。
しかし裁判所は、会社法上の整理を踏まえ、名義書換がされていないことだけで「議決権がない」とは扱えない、と判断しました。
さらに、その判断は、会社が正当な理由なく名義書換請求を拒絶していた場合には、会社は実質的にその者を株主として取り扱うべきだ、という最高裁判例の考え方も踏まえたものとなっています。
本文でも、次のように述べています。
戊贈与株について名義書換えがされていなかったことをもって、その議決権を有しないものと取り扱うのは相当でない。
結果として、配当還元方式は否定され、類似業種比準方式で評価すべき、という結論になりました。
税務判断は、「事実感覚だけで突っ走らない」ようにしましょう。
配当還元方式が使えるかどうかは税額に直結しやすいため、相続発生後に「名義書換が終わっていないから配当還元方式で」と短絡的に判断しないことが重要です。
 想う相続税理士
想う相続税理士