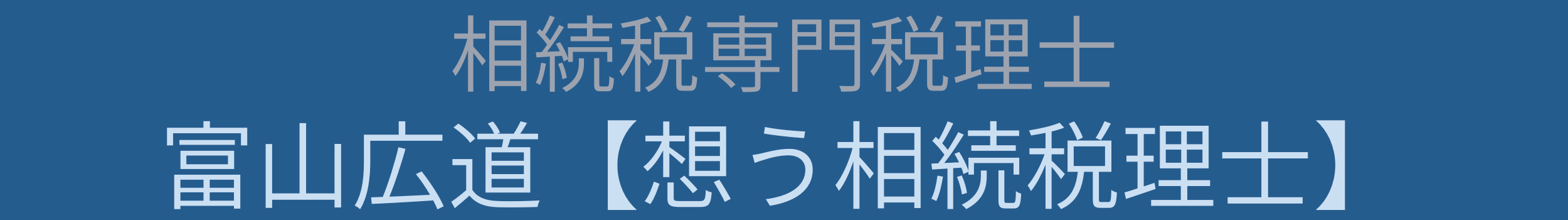相続税専門税理士の富山です。
今回は、区分所有建物(商業ビル)の敷地に係る「借地権の持分」を、階層別の収益性(効用比率)で調整して評価できるのかが争われた裁決事例について、お話します。
出典:TAINS(F0-3-597)(一部抜粋加工)
平29-11-17裁決
共有財産の持分は持分割合で按分する
相続税は、原則として「相続開始時点の時価」で財産を評価します。
ただし、実務では評価の統一性や公平性の観点から、財産評価基本通達(評価通達)に従って評価するのが通常です。
本件は、区分所有建物(商業ビル)の7階・8階部分を相続したケースで、その敷地利用権が「借地権の持分(共有持分)」でした。
請求人(相続人側)は、低層階の方が収益性が高いのだから、階層別の利用率(効用比率)を使って、借地権持分の評価額も調整すべきだと主張しました。
しかし裁決では、借地権全体の評価額を算定し、それに持分割合(本件では9分の2)を乗じて評価するのが相当と判断されています。
この場面でのポイントは、「共有財産の持分は、持分割合で按分する」という考え方です。
低層階の優位性、建物構造、路線価格差は加味される?
請求人側は大きく2つの事情を挙げました。
1つ目は、繁華な商業地域では、低層階が高層階よりも店舗として優位で、賃料等の収益性が大きく異なるという点です。
2つ目は、建物構造上、3階以上は裏面道路からしか入室できない一方で、地下1階から2階は正面道路から出入りできるため、正面路線と裏面路線の路線価の大きな差(約5対1)を踏まえると、価値・収益性に明確な差があるという点です。
つまり、「同じビルでも階層によって稼ぐ力が違うのだから、借地権の価値も階層別に変わるはずだ」という発想です。
このロジックに近い評価手法として、公共用地の取得に伴う損失補償の世界で用いられる「建物階層別利用率(効用比率)」を持ち込み、借地権持分の評価にも掛け算して調整しようとしました。
実務感覚としても、収益性の差が大きいビルほど「階によって価値が違うのに、同じ扱いでよいのか」と感じやすいところです。
しかし、相続税評価でそれが通るかどうかは、別問題になります。
階層差は持分の質を変えない
裁決は、請求人の主張する「収益性の差」自体を真正面から否定した訳ではありません。
低層階の方が商業上有利で賃料に差が出ることは、商業地域のビルでは一定程度あり得る、と整理しています。
しかし、それは一般的傾向にとどまり、評価通達に基づく評価が「時価を適切に反映していない」と直ちにいえる事情には当たらない、と判断しました。
より重要なのは、敷地利用権が「借地権そのもの」ではなく、「借地権全体に対する持分(共有持分)」だという点です。
区分所有建物が低層階であっても高層階であっても、借地権全体に対して有する権利は持分割合に応じて均等で、質的に異なるところはない、という整理がされています。
そのため、「所有している専有部分が何階か」という事情を理由に、借地権持分の評価だけを効用比率で動かすことは相当ではない、と結論づけています。
また、損失補償基準(細則)の効用比率を用いることについても、そもそも同基準は公共事業に伴う損失補償のための枠組みであって、相続税評価に転用する根拠が明確ではない、としています。
本文中でも、評価の枠組みが「評価通達」を中心に組み立てられていることが読み取れます。
評価通達2は、共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価すると定めている。
さらに、損失補償基準の位置づけについて、次のように述べています。
損失補償基準は、各事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償の基準を定め
「収益性の差がある」ことで「相続税評価を通達から外して調整できる」ようになるためには、相当に大きなハードルがあります。
 想う相続税理士
想う相続税理士
しかし、相続税評価は、まず評価通達の枠組みで説明できるかが出発点になります。
とくに「借地権そのもの」ではなく「借地権の持分」をどう捉えるかで、理屈の組み立て方は大きく変わります。
評価の前提(権利の性質)が何かを丁寧に確認し、通達評価から外す主張をするなら、どこがどのように(通達評価から外すべき)「特別の事情」なのかを、証拠とともに慎重に検討することが重要です。