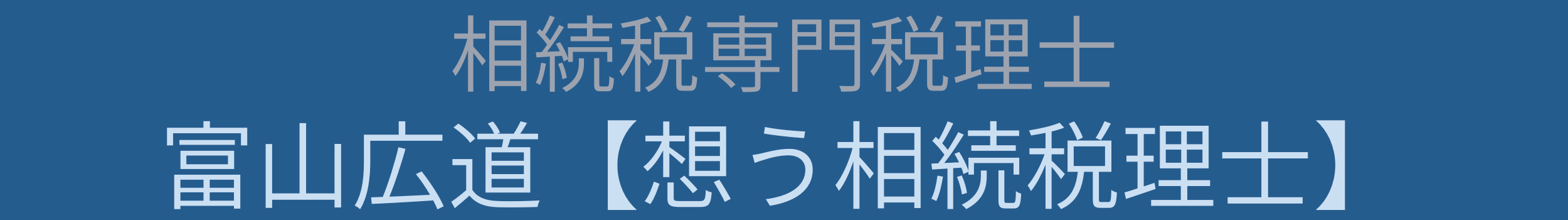相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続した集合住宅の空室部分が「一時的空室」に該当するかどうかについて争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z267-12988)(一部抜粋加工)
平成29年3月7日判決
「一時的空室」に該当すれば相続税が安くなる
相続税では、財産の金額は原則として「相続開始時点の時価」で評価します。
アパートやマンションのような賃貸物件は、借家権などの制約があるため、一般に自用(自分で自由に使える状態)よりも経済的価値が低くなると考えられます。
そのため、財産評価基本通達では「貸家」や「貸家建付地」について一定の評価減(減額)が認められています。
ただし、その評価減は「課税時期(相続開始日)に実際に賃貸されている部分」を前提に計算します。
ここで問題になるのが、相続開始日に「たまたま」空いていた部屋をどう扱うか、という点です。
本件では、被相続人(亡くなった方)が所有していた集合住宅について、相続人側は「空室部分も含めて全体が賃貸部分だ」として申告しました。
一方、税務署側は「空室部分は賃貸部分ではない」として更正処分等を行いました。
争点は、空室部分が財産評価基本通達26(注)2の「一時的空室部分」に当たるかどうかでした。
財産評価基本通達(一部抜粋)
26 貸家建付地の評価
2 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。
空室期間は、短いものでも2ヶ月と23日、長いものでは23ヶ月と14日に及んでいました。
「一時的空室」とはどんな状況?
判決は、評価減の趣旨を「賃貸借契約による制約があると経済的価値が下がるから」と整理した上で、空室がある部分については、その制約がない以上、原則として価値は下がっていないと考えました。
そして、「一時的空室部分」は例外的に「賃貸されているのと同視できる場合」に限って認められる、という考え方を示しています。
ポイントは、「相続開始時点で、近い将来に相当期間の賃貸借契約が成立する具体的な見込みが客観的にあったか」です。
この点について、判決は次のように述べています。
証拠に照らしても、本件各空室部分は、上記課税時期の時点で、その全部又は一部につき特定の者との間で賃貸借契約の締結に向けた具体的な交渉をしていたなどの事実が認められない以上、上記②にいう、同時点を基準として、その後の近接した時点で賃貸借契約が締結される具体的な見込みがあったと認めるには足りないというほかない。
本件では、相続開始日時点で「特定の者との具体的交渉」などが認められず、また相続人側自身も「供給過剰で簡単に決まる状況ではなかった」と主張していました。
そのため、空室部分は「課税時期に賃貸されていたと実質的に同視できない」とされました。
結論として、空室部分は「一時的空室部分」には当たらず、賃貸割合に含められない、と判断されています。
「一時的空室」に該当するかどうかの判断要素
相続により賃貸物件を引き継ぐケースは、決して珍しくありません。
そして、相続開始日には、複数の部屋が空いていることも現実にはよくあります。
この場合、「普段は貸しているのだから、空室もまとめて貸家として評価できるはず」と思ってしまいがちです。
しかし、本件判決が示すとおり、空室がいつでも一時的空室として取り扱える訳ではありません。
特に、空室期間が長い場合や、相続開始時点で具体的な成約見込みが弱い場合は、賃貸割合に入れられないリスクが高まります。
実務上は、次のような観点で整理しておくことが重要です。
相続開始前の近い時点まで、どのくらい継続して賃貸されていたか。
退去後、募集や原状回復をどの程度速やかに行っていたか。
相続開始時点で、申込み、内見、条件交渉など「特定の相手との具体的な動き」があったか。
相続開始後の賃貸が、どれくらい近接した時点で成立し、どの程度の期間の契約になっているか。
これらは、後から「募集はしていました」と口頭で説明しても、客観資料が乏しいと評価に反映されにくくなります。
募集広告、仲介会社とのやり取り、修繕記録、内見の予定表、申込書など、事実関係を裏付ける資料の残し方が重要になります。
 想う相続税理士
想う相続税理士
つまり、「別の制度でこう扱うから、評価でも同じだろう」という発想は危険で、制度ごとの目的の違いを踏まえて整理する必要があります。