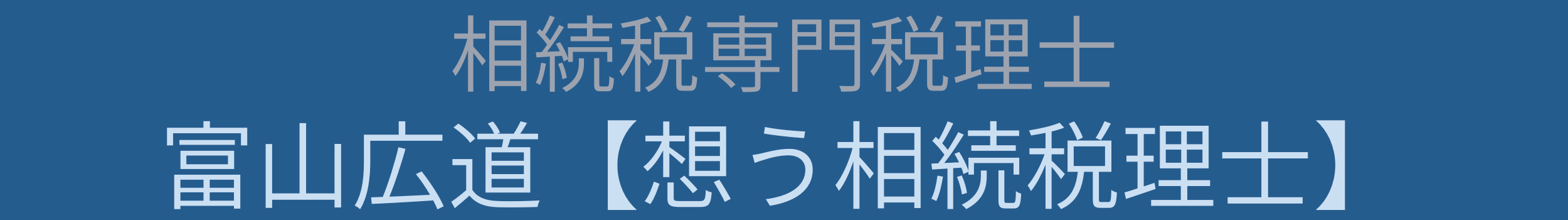相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例における「亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等」が「2ヶ所でも認められるか」が争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z259-11137)(一部抜粋加工)
平成21年2月4日判決
居住の用に供されていた宅地等が複数あったらダメ?
本件は、相続で取得した2つの土地について、どちらも被相続人(亡くなった方)が「居住の用に供していた」として、小規模宅地等の特例(居住用宅地等)を適用して申告したところ、税務署長が「特例の対象は1ヶ所しか認めない」として更正した事案です。
争点は、特例の対象となる「居住の用に供されていた宅地等」が「主として居住の用に供されていた宅地等」に限られるのかどうか、という点でした。
この点について高裁は、「主として」という限定はできない、という解釈自体は認めつつ、結論としては、二つの宅地の両方が「居住の用に供されていた」とは認められないとして、納税者の主張を退けました。
つまり、制度解釈の入口は納税者側に一定程度寄りつつも、最後は「事実(実態)」で負けた、という構図です。
当裁判所も、本件特例の適用の対象となる「居住の用に供されていた宅地等」は、「主として居住の用に供していた宅地等」に限られないものと判断する。その理由は、原判決14頁24行目の「税務調査会」を「税制調査会」と改め、同15頁7行目の「ものであり」の後に「(乙16)」を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
出典:TAINS(Z258-10956)(一部抜粋加工)
相続税と所得税の特例という違いはあるものの、所得税の場合には、措置法31条の3第2項に「居住の用に供している(家屋)」という文言があり、これについて規定する措置令20条の3第2項において、「その者がその居住のように供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。」と規定しているにもかかわらず、本件特例においてはそのような制限はされていないことからすると、本件特例の解釈として、主として居住の用に供されていた宅地等に限るとすることは困難であって、面積要件さえ満たせば、複数存在することも許容されていると解するのが相当である。
例えば、貸付地については、事業に至らない場合にまで拡大されたりしているのであるから、本件個別通達に存在した「主として」という文言が本件特例では削除されているということは、文字どおり、本件個別通達の「主として」の制限を本件特例で解除したものにほかならないものというべきである
さらに、本件のような相続税における小規模宅地等の課税の特例における居住用宅地については、1回限りの相続において、面積要件もあることや、居住の継続の要件もないこと(すなわち売却も可能)からすると、譲渡所得の特例の場合のように、主たるものに制限しなければならない理由に乏しいのであって、この点からも、ことさらに無理をして、本件特例の適用の対象となる「居住の用に供されていた宅地等」を「主として居住の用に供していた宅地等」に限定する解釈を行う必要性もない。
「居住の用」かどうかは何で決まるのか?
この判決が実務上とても参考になるのは、「居住の用に供されていた」かどうかの判断枠組みを、かなり具体的に示している点です。
ポイントは、「住民票があるか」「家があるか」ではなく、被相続人がその建物に「生活の拠点」を置いていたか、という実態で判断する、という考え方です。
本件特例の「居住の用に供されていた」宅地に当たるかどうかについては、被相続人が生活の拠点を置いていたかどうかにより判断すべきであり、具体的にはその者の日常生活の状況、その建物への入居の目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判断されるべきである。
そして本件では、別宅(マンション)について、設備が整っていた事情は一定程度認めつつも、実際の利用状況が散発的であったこと等から、「生活の拠点」とは言えないと評価されました。
さらに、郵便物の届き先、金融機関や取引先への届出、電気・ガス・水道の使用量といった、生活実態を示す周辺事情が重視されている点も見逃せません。
要するに、「いつ・どれくらい・どんな目的で・そこで生活していたのか」を、客観資料を含めて総合判断される、ということです。
生活の拠点はどこか?を前もって検討しておく
生前において、被相続人に自宅とは別の住まい(マンション、アパート、子の家の一部、週末の拠点等)がある場合、小規模宅地等の特例をどちらに適用できるかは、申告段階で揉めやすい論点となり得ます。
別宅側を「居住の用」と主張するのであれば、少なくとも次のような観点で説明できるかを意識しておく必要があります。
そこでの日常生活が、どの程度の頻度と継続性をもって営まれていたかどうか
生活の拠点を示す外形(郵便物、各種届出、公共料金の利用状況など)に、無理のない整合性があるかどうか
もちろん、病気等の事情で利用が減った時期があること自体は現実に起こり得ますが、それでも「生活の拠点だった」と言えるだけの土台があるかが問われます。
 想う相続税理士
想う相続税理士