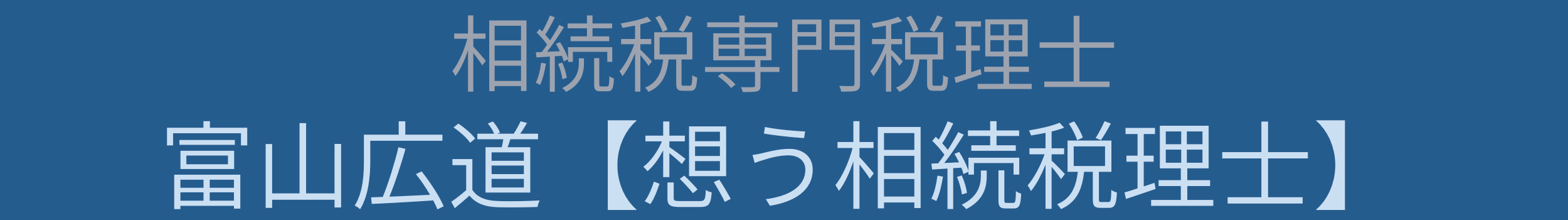相続税専門税理士の富山です。
今回は、同族会社株式の評価に相続後の決算の数値が使えるかどうかについて争われた裁決事例について、お話します。
出典:TAINS(F0-3-900)(一部抜粋加工)
裁決年月日:令05-07-05裁決
同族会社株式の評価をめぐる争い
この裁決は、共同相続人が同族会社(中会社)の株式を相続した事案です。
相続税の申告当初は、評価通達(財産評価基本通達)どおりに評価明細書を作成し、Lの割合や比準要素・1株当たりの純資産価額を求めて「併用方式」で株価を計算して申告していました。
その後、相続人側は「この評価は高すぎるのではないか?」と考え、更正の請求をしました。
ポイントは、どの時点の会社の数値を基準として使うか、という点です。
相続人側は、相続開始の直後に終了した事業年度(直『後』期末)の決算数値を使い、Lの割合を0.9とすることで、1株あたりの価額を引き下げられると主張しました。
これに対し、税務署側(原処分庁)は、評価通達に定めるとおり直『前』期末を基準とした併用方式で評価すべきであるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行いました。
納税者側はこの通知処分を不服として審査請求を行い、国税不服審判所で争われたのが本件裁決です。
争点は、取引相場のない同族会社株式について、評価通達の直『前』期末の数値を用いる取扱いが合理的といえるかどうか、そして、相続後の直『後』期末の数値を使う余地があるのか、という点にありました。
評価通達の考え方と審判所が示した「合理性」の枠組み
裁決では、まず評価通達そのものの位置づけが丁寧に整理されています。
相続税法第22条は、
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により
としていますが、財産の種類は多様であり、個別に時価を算定すると、実務上も課税の公平の面でも大きな問題が出てきます。
そこで、評価通達により「画一的な評価方法」を定め、その方法が一般的に合理的である限り、その評価額を時価として扱う、という実務が取られていることを改めて確認しています。
取引相場のない株式についても同様で、原則として、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社はその中間として、類似業種比準方式と純資産価額方式をLの割合で組み合わせる「併用方式」が採用されています。
この併用方式やLの割合(0.90・0.75・0.60)は、会社の事業規模に応じて評価方法を段階的に変えることで、大会社・中会社・小会社の間で評価額に不自然な断層が生じないよう設計されている、と裁決は説明しています。
また、事業規模の判定に用いる総資産価額・従業員数・取引金額について、評価通達は「直『前』期末」や「直『前』期末以前1年間」の数値を使うこととしています。
その理由として、裁決は、相続開始後の株価や業績を評価に反映させると、相続開始後に恣意的な操作が行われるおそれがあり、課税の公平を害することになる、と指摘しています。
この点を踏まえたうえで、審判所は次のように述べています。
以上によれば、本件株式に係る評価通達の定める評価方法は、適正な時価を算定する評価方法として一般的な合理性を有するものであると認められる。 また、本件株式の価額が評価通達の定める評価方法に従って決定された場合には、本件株式は、適正な時価を求めることができない結果となるなど、同通達の定める評価方法によるべきではない特別の事情は認められない。 そうすると、本件株式の価額について、評価通達の定める評価方法に従い算定された本件株式評価額は、本件株式の適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができ、本件株式は、同通達の定める評価方法によって適正な時価を算定することができる。
つまり、この裁決では、
その評価方法による限り、特別な事情がない限りは「適正な時価」と推認されること
相続後の決算数値は使えないのか?実務への示唆と注意点
では、相続人側が主張した「相続後の直後期末の数値を使うべきだ」という考え方は、なぜ退けられたのでしょうか?
相続人側は、課税時期と同じ年に終了する直後期末の方が、会社の実態をより正確に反映している、と主張しました。
しかし裁決は、評価通達が相続開始後の株価や業績の変動を考慮していない理由として、
そのような「後出し」の数値を認めると、納税者間の公平が保てなくなること
そして、納税者側の計算方法は、評価通達の枠組みの中で「より合理的な評価方法」とまではいえず、特別の事情があるとも認められないと判断されました。
 想う相続税理士
想う相続税理士
同族会社株式の相続税評価は、「直後期末の方が実態に近いから(同一年だから)」という理由だけで評価通達から外れることは認められにくいですので、ご注意を。