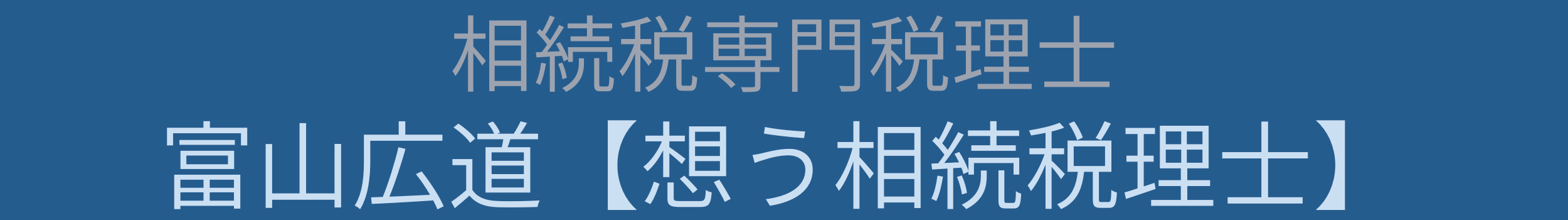相続税専門税理士の富山です。
今回は、取引相場のない株式の評価において、会社が所有する特殊な資産の評価が争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z270-13458)(一部抜粋加工)
令和2年10月1日判決
鑑定方法にもいろいろある
本件は、母からE社株式(取引相場のない株式)の贈与を受けた納税者が、「株価は0円」として贈与税申告をしなかったところから始まります。
税務署は、E社が保有する外国子会社の資産に着目しました。
その外国子会社は、定期傭船契約(一定期間、定額の傭船料を受け取る契約)が付いた船舶を多数所有していました。
税務署は「船舶の価額を適正に評価すれば株価は高額になり、贈与税が発生する」として贈与税の決定処分等を行いました。
争点は、贈与日(平成21年2月28日)時点での船舶(売却予定の3隻を除く67隻)の価額でした。
ポイントは、「定期傭船契約付き船舶の価値を、どうやって客観的に評価するか」です。
この事案では、税務署側の鑑定(取引事例比較法や建造船価償却法)と、納税者側の鑑定(収益還元法=DCF法)が対立しました。
そして裁判所は、財産評価基本通達136(船舶の評価)に沿って「精通者意見価格を参酌する」こと自体は合理的としつつも、どの鑑定が「精通者意見価格として参酌できるほど合理的か」を丁寧に検討しています。
評価方法よりも評価過程の合理性の有無が重要
裁判所は、定期傭船契約付き船舶について「契約が評価時以降も存続する蓋然性がある限り、契約で見込まれる収益価値を考慮して評価するのが相当」と整理しています。
つまり、船体だけを「カラ船」として見るのでは足りず、傭船料収入や費用、契約終了後の売却価値も含めた見方が重要、という方向性です。
そのうえで裁判所は、方式としては「取引事例比較法」と「収益還元法(DCF法)」のいずれも合理性を有し得る、と述べています。
ただし問題は「方式の名前」ではなく、「その方式で、どんな前提・調整・補正をしているか」です。
税務署側の鑑定のうち、取引事例比較法については、定期傭船料に関する調整対象期間を「3年に限定」していた点が焦点になりました。
裁判所は、残存傭船期間が3年を超える船舶について、4年目以降の調整を全くしないのは収益価値の正当な評価を損なうとして、合理性を欠くと判断しています。
その結果、取引事例比較法が適用された33隻のうち、残存傭船期間が3年以下の10隻に限っては参酌できるが、3年超の23隻は参酌できない、という整理になりました。
また、税務署側が別の船舶に用いた建造船価償却法についても、造船契約締結時から評価時までの市況変化の補正がないのに用いた点が問題視されています。
裁判所は、評価時点の価格を求めるのに、過去の建造時の市況を反映した数字を補正なしで使うのは合理性を欠くと判断しました。
一方で、納税者側の鑑定(収益還元法・DCF法)については、残存傭船期間、傭船料のレンジ設定、船舶管理費の設定、割引率(リスクプレミアム)など、税務署側が疑問を呈した点を個別に検討し、全体として不合理な点はうかがわれないとして参酌可能としました。
ここで重要なのは、「精通者が作った鑑定書だから採用される」のではなく、「評価の目的に照らして、前提とロジックが合理的か」が問われる、という点です。
簡単に評価できない資産があると申告が大変
この判決は贈与税の事案ですが、相続税の申告でも「取引相場のない株式」を評価する場面は頻繁に出てきます。
そして非上場株の評価は、会社の「中身」である資産・負債の評価次第で大きく変わります。
本件では、外国子会社が多数の船舶を保有し、しかも定期傭船契約が付いているという特殊性がありました。
こうした特殊資産は、評価の前提や補正の仕方ひとつで、数百億円単位の差になり得ることが示されています。
また、財産評価基本通達が「精通者意見価格を参酌」と書いていても、鑑定書なら何でもよいわけではありません。
調整対象期間をどう置くのか。
市況変化を補正しないでよい特段の事情があるのか。
傭船料・費用・割引率の設定が、評価時点の状況に照らして説明できるのか。
こうした点が積み上がって、最終的に株価がプラスになるか、ゼロになるかが決まっていきます。
相続税の申告でも、会社または亡くなった方(または推定被相続人)が特殊な資産を持っている場合には、早い段階で「評価の論点」を洗い出し、必要なら専門家の意見(鑑定等)をどう位置付けるかを設計しておくことが、後日の争いを減らす上で有効です。
 想う相続税理士
想う相続税理士