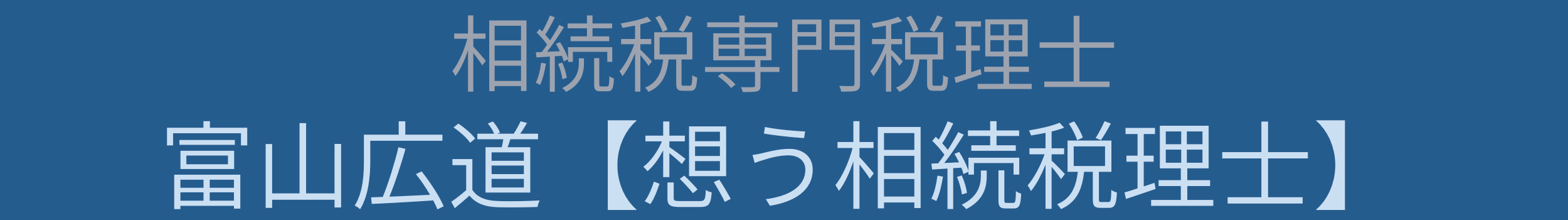相続税専門税理士の富山です。
今回は、和解により将来免除される借入金が相続税の申告において債務控除できるのかが争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z888-2757)(一部抜粋加工)
令和6年11月28日判決
問題となった借入金とは?
この判決は、被相続人(亡くなった方)の借入金の一部について「一定の条件を満たせば将来免除される」ことになっていたケースについてのものです。
亡くなった方の父(「父A」とします)が銀行から約16億円を借り入れ、その借入金をめぐって銀行との間で訴訟となりました。
訴訟の途中で父Aが亡くなり、相続人が訴訟を引き継いだ上で、銀行との間で訴訟上の和解が成立しました。
和解では、借入金のうち約6億2,630万円を一定のスケジュールで支払う代わりに、残りの約9億7,370万円は、条件どおり支払いが行われれば免除される、という内容になっていました。
その後、被相続人は和解の支払条件に従って支払いを続け、相続開始時点で残っていた支払額は合計100万円だけ、という状況になっていました。
相続開始後、相続人はこの借入金のうち、将来免除される予定の9億7,370万円部分も含めて(100万円+9億7,370万円=9億7,470万円)、相続税の申告において債務控除の対象としました。
ところが税務署は、この9億7,370万円の部分は相続税法第14条第1項の「確実と認められる」債務には当たらないとして、更正の請求を認めず、「更正をすべき理由がない旨の通知処分」を行いました。
そこで相続人は、「この部分も債務控除できるはずだ」と主張して処分の取消しを求め、争いになったのがこの事件です。
裁判所が考えた「確実と認められる債務」とは?
相続税法第13条第1項は、「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」の金額を、相続財産の価額から控除できると定めています。
しかし、相続税法第14条第1項には「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。」と書かれています。
この「確実と認められる」の中身が争点となりました。
裁判所は、まず債務控除の趣旨について、次のように述べています。
被相続人の債務の金額は取得財産の価格から控除されるが、その趣旨は、その債務の弁済に必要な資金を課税対象外として相続人に留保させ、担税力に配慮した公平な課税を行うためであると解される。そうすると、存在が確実な債務であっても、その性質上、相続人が履行するとは限らず、必ずしも相続人ないし相続財産の負担とはならないものは、原則として、控除すべき債務の対象から除かれなければならないということになる。したがって、相続税法14条1項の「確実と認められる」債務とは、債務が存在するだけでなく、その履行が確実と認められる債務を意味すると解すべきである。
つまり裁判所は、「確実と認められる債務」とは、単に「債務が法律上存在している」というだけでは足りず、「その債務を実際に支払う(履行する)ことが確実である」ことまで必要だ、と解釈しました。
この点に対して納税者側は、「条文の文言からすると、確実かどうかを検討する対象は『債務の存在』だけであり、履行まで要求するのは租税法律主義に反する」と主張しました。
しかし裁判所は、相続税法第13条第1項第1号で既に「相続開始の際現に存するもの」と債務の存在を別に規定していることなどを踏まえ、「第14条第1項は趣旨目的に即して解釈すべきであり、履行の確実性まで求める解釈は租税法律主義に反しない」として、納税者側の主張を退けました。
では、この事件で問題となった「将来免除される予定の9億7,370万円」について、裁判所はどう考えたのでしょうか?
本件では、相続開始時点で、和解に基づく分割金の残額は100万円だけであり、相続人は本件相続によってそれぞれ約8億4,700万円、約10億7,500万円という多額の財産を取得していました。
裁判所は、この財産状況からすれば、残り100万円を支払うことは容易であり、和解条項にしたがって近い将来に債務免除が行われる可能性が極めて高かった、と判断しました。
その結果、問題となった9億7,370万円の債務については、「履行がされない可能性が極めて高かった=支払うことが確実とは言えない」として、相続税法第14条第1項の「確実と認められるもの」に当たらないと結論付けました。
したがって、この9億7,370万円は、相続税の課税価格から控除することができる債務には含まれない、という判断になっています。
債務免除益にかかる所得税は相続税の債務控除になるか?
この事案ではもう一つ、大きな論点がありました。
相続開始後、相続人が和解条件どおり支払いを完了した結果、9億7,370万円の債務が免除され、その分について相続人に「債務免除益」が生じました。
税務署は、この債務免除益を一時所得として所得税等を課税しており、相続人はその所得税等を納付しています。
そこで相続人側は、「将来この債務免除益に所得税がかかることは相続開始時に高い蓋然性をもって予見できたのだから、その所得税相当額については、相続税の計算上『公租公課』として債務控除の対象にすべきだ」と主張しました。
これに対して裁判所は、相続税法第14条第2項及び相続税法施行令第3条第1項を確認した上で、次のような結論を示しています。
相続税法14条2項は、債務控除の対象となる「公租公課」(同法13条1項1号かっこ書)について、被相続人の死亡の際に確定しているもののほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする、としている。そして、当該政令として定められた同法施行令3条1項をみても、被相続人の死亡後に発生した、相続人に課せられる債務免除益に係る所得税等が、債務控除の対象となる「公租公課」に当たるものとした規定は見当たらない。したがって、本件債務免除益に係る所得税等は、債務控除の対象となる「公租公課」に該当しないのであり、これを原告らの本件相続税から控除することはできない。
ポイントは2つです。
1つ目は、債務控除の対象となる「公租公課」は、原則として「被相続人に係る税金」であることです。
本件の債務免除益は、相続開始後に相続人に生じた所得であり、それに対する所得税は「被相続人ではなく相続人に課された税金」です。
2つ目は、相続税法施行令第3条第1項の列挙やそれに準ずる範囲をみても、こうした相続人に課される債務免除益の所得税等は含まれていない、という点です。
そのため、債務免除益にかかる所得税等については、相続税の計算上、公租公課として債務控除することはできない、と判断されました。
最終的に裁判所は、税務署長が更正の請求を認めなかった各通知処分はいずれも適法であるとして、納税者側の請求を棄却しました。
 想う相続税理士
想う相続税理士
将来免除される予定の借入金や、条件付きの債務については、相続開始の時点で本当に相続人の負担になるといえるのかどうか、財産状況や契約内容を踏まえて慎重な検討が必要です。