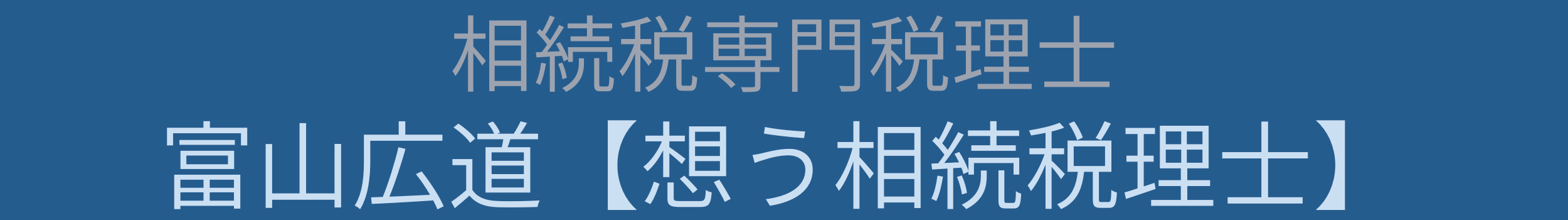相続税専門税理士の富山です。
今回は、主建物と附属建物がある土地について、「敷地は1つとして評価すべきか」それとも「2つに分けて評価すべきか」が争われた裁決事例について、お話します。
出典:TAINS(J93-4-13)(一部抜粋加工)
平25-10-1公表裁決
貸家建付地評価と評価単位
相続税の土地評価は、見た目が同じ土地でも「どう使われているか」によって評価が変わることがあります。
今回の裁決では、大きく2つの争点がありました。
1つ目は、その土地全体に「貸家建付地」の評価(評価減)を使えるのか、という点です。
2つ目は、その土地を「1画地」として評価するのか、「2画地」に分けて評価するのか、という点です。
本件では、土地の上に建物があり、その建物は登記上「主たる建物」と「附属建物」が記載されていました。
しかし、登記の書き方だけで敷地の評価単位(1つか2つか)が決まるわけではない、というのが結論の方向性になります。
また、賃貸されている建物が亡くなった方と相続人の共有になっており、敷地が「貸家建付地」にならない点が、実務上とても重要です。
「現況」と「権利関係」が、土地評価の分かれ道になっています。
土地の上の建物を貸していても土地は「自用地」扱い
本件では、土地の所有者(亡くなった方)と、建物の共有者(相続人の一人)との間で、土地について賃貸借契約は結ばれていませんでした。
裁決では、この関係を「使用貸借」(無償で借りて使う関係)と認定しています。
そして、使用貸借に基づく敷地利用権が付着する土地については、「減価を考慮せず更地(自用地)として評価する」という取扱いが示されています。
本件でも、建物が第三者に賃貸されていた事情があっても、土地の一部については貸家建付地ではなく、自用地として評価すべきだと判断されました。
裁決の考え方が表れている箇所を、本文から一部引用します。
使用貸借は、元々当事者間の好意ないし個人的信頼関係を基盤とするもので、建物所有を目的とするものといえども、賃借権のように借地借家法の適用はなく、その権利性はそれほど強固なものではない。そして、この使用貸借に基づく敷地利用権の上に、建物の賃貸借関係が成立しているとしても、この建物賃貸借は、敷地所有者との関係でみると、使用貸借の存続・消滅と運命をともにするものにすぎない。
難しく見えますが、要点はこうです。
土地の所有者から見れば、土地の使用関係が「賃貸借」なのか「使用貸借」なのかで、土地の自由度が違う、という整理です。
その違いが、土地の評価に影響し得る、ということになります。
実務では、親族間取引により「土地は無償で使っている」というケースが紛れやすいので注意が必要です。
契約書がなくても、経緯や実態から使用貸借と評価されることがあり得ます。
土地評価を組み立てる前に、「土地の使用関係の契約がどうなっているか」を必ず確認しておきたいところです。
登記が「主」「附属」でも、敷地が2画地に分かれることがある
次の論点は、評価単位(1画地か2画地か)についてです。
原処分庁は、登記上の「主」「附属」の関係や、住宅地図で接して見えることなどを理由に、1画地評価を主張しました。
一方で、裁決では、建物が別棟で接しておらず、それぞれ独立して機能していたこと、そして別々の第三者に貸し付けられていたことが重視されました。
本文中の結論部分を、一部引用します。
以上のとおり、評価通達7-2の(1)の定めによれば、本件土地については、本件主建物の敷地部分と本件附属建物の敷地部分とが別の利用の単位と認められることから、請求人らの主張のとおり別図1に基づき、2画地の宅地として評価するのが相当である。
つまり、ポイントは「登記の形式」よりも「現況(配置・機能・貸付けの実態)」だった、ということです。
敷地を2画地に分けるかどうかは、評価額に直結するため、申告の前提が大きく変わります。
特に、同じ敷地内に建物が複数あり、しかもテナントや入居者が別々に存在する場合は、評価単位の検討が必須です。
現地確認、配置図、賃貸借契約の相手方、利用状況など、判断材料を揃えて評価の根拠を組み立てることが重要になります。
「主建物・附属建物だから一体評価でよい」と短絡的に判断・評価すると、評価をミスるリスクがあります。
相続税申告では、早い段階で土地の評価方針(権利関係と評価単位)を設計しておくことが安全です。
 想う相続税理士
想う相続税理士