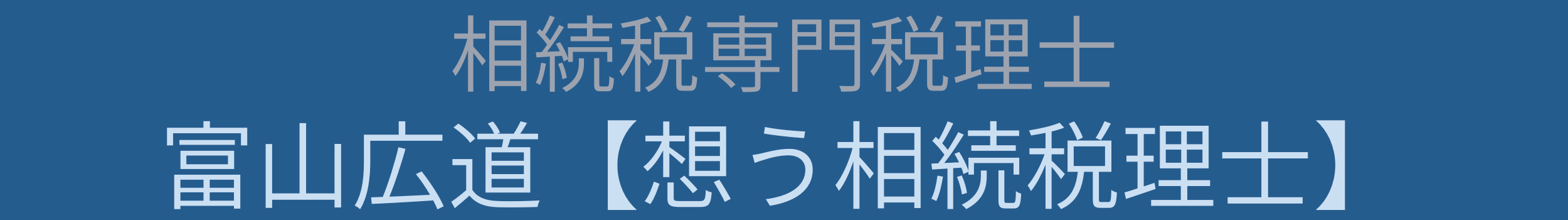相続税専門税理士の富山です。
今回は、1つの建物の中に「居住」「貸付事業」「事業(店舗等)」が混在するケースにおける、小規模宅地等の特例の対象となる宅地の「区分」と「選択」の考え方について、お話します。
出典:国税庁HP・その他法令解釈に関する情報/TAINS(相続事例707376)(一部抜粋加工)
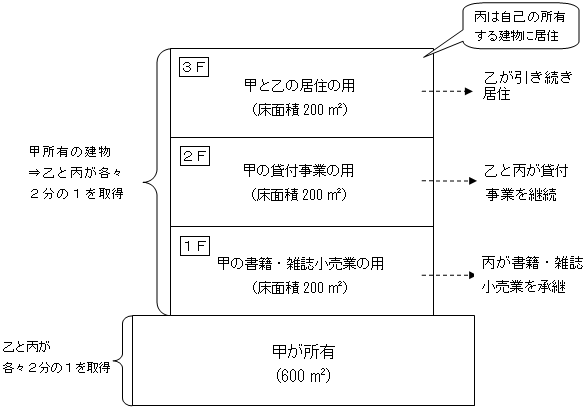
「宅地『全体』」ではなく「利用区分ごとの『部分』」を確認していく
小規模宅地等の特例は、「土地が1筆だから一括で判定する」と考えてしまうと、判断を誤ってしまいます。
今回の事例では、土地600㎡の上に建物1棟があり、3階が居住、2階が貸付、1階が小売業という形で「利用区分が縦に分かれている」前提です。
このとき、まず行うのは「宅地全体を、居住用・貸付事業用・事業用・それ以外に区分する」ことです。
そして、その区分は、建物の利用状況に対応させて、床面積などの合理的な基準で宅地を按分していくのが基本になります。
一見すると「床面積按分さえすれば終わり」に見えますが、実務では次の落とし穴があります。
それは、同じ建物でも、相続人ごとに「特例の対象として選べる区分」が変わる点です。
共有で相続すると「相続人ごと」に区分判定が必要
今回の素材では、配偶者乙と子丙が、土地と建物をそれぞれ2分の1ずつ共有で取得し、申告期限まで保有しています。
ここで重要なのは、「誰がどの事業を承継し、申告期限まで継続したか」です。
たとえば乙は居住を継続し、貸付事業も引き継いで継続しています。
一方で、書籍・雑誌小売業(事業)は丙が承継し、継続しています。
この違いにより、乙が取得した1階部分相当は「事業用としては扱えず、特例の適用がない」ということになります。
同様に、丙が取得した3階部分相当は「居住用の要件を満たさないため、特例の適用がない」ということになります。
つまり、共有で同じ土地を相続していても、相続人ごとに(今回のケースでは)、
「特定居住用として選べる部分」
「貸付事業用として選べる部分」
「特定事業用として選べる部分」
「それ以外(減額対象にならない部分)」
が分かれてしまう、ということです。
「選べる部分」が複数あっても、全部は選べないことがある
今回の事例でも、結論としては、乙・丙それぞれについて、特例の選択が可能な区分が複数ある形になります。
しかし同時に、限度面積要件があるため、選択可能な部分をすべて特例対象にできるとは限らない点が明示されています。
この「選択」の局面では、「要件を満たす区分がある=自動的に全部が減額される」という訳ではない点に留意が必要です。
実務的には、まず区分の整理を正確に行い、次に「どの区分を、どの面積まで選択するのが合理的か」を、限度面積要件を踏まえて設計していく流れになります。
相続税申告の場面では、土地の評価や遺産分割と並行して検討が進むため、こうした「区分と選択」の論点が後回しになりがちです。
しかし後回しにすると、申告期限が近づいた段階で「この部分はそもそも選べない」「全部は選べない」が発覚し、分割案や納税資金計画に影響が出ることがあります。
建物が1棟で用途が複数ある場合は、早い段階で、
申告期限まで継続できる見込みか
土地のどの部分がどの区分に対応するか
限度面積要件の中で、どこを優先して選ぶのか
をセットで整理することが重要です。
 想う相続税理士
想う相続税理士
特に共有で相続する場合は、相続人ごとに「承継した内容」と「継続の事実」が問われ、選べる区分が変わります。
さらに、選べる区分が複数あっても、限度面積要件の中で「どれを選ぶか」を設計しなければならない局面が出ます。
不動産の使い方が複雑な場合は、早めに区分整理の見取り図を作ることが、申告直前の混乱を防ぐ最短ルートです。