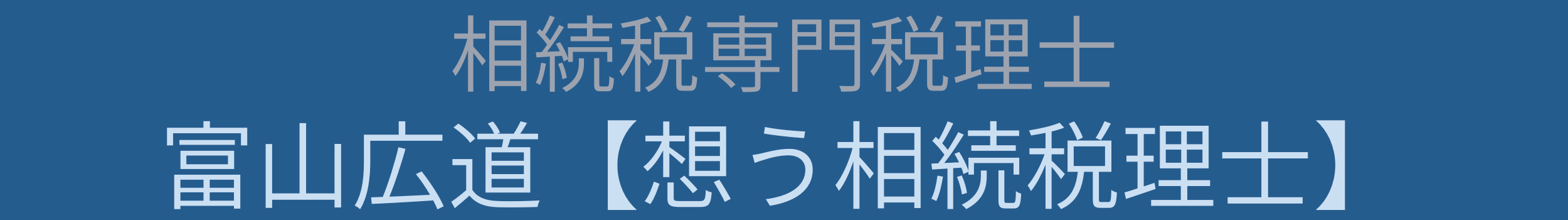相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における同族会社に対する貸付金債権の評価(回収可能性)が争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z271-13503)(一部抜粋加工)
令和3年1月13日判決
財産評価基本通達における貸付金の評価方法
相続が起きると、預金や不動産だけでなく、「亡くなった方が誰かに貸していたお金」も相続財産になります。
特に、家族経営の会社(同族会社)に対する貸付金は、借用書が曖昧でも、長年の資金繰りの中で残高が積み上がっていることが少なくありません。
そして怖いのは、「どうせ返ってこないものだから」と思って相続税申告で計上しない、またはゼロ円に近い評価で申告しようとしてしまうことです。
本件では、被相続人(亡くなった方)が代表者を務めていた同族会社に対する貸付金債権について、納税者側が課税価格に計上せず申告したところ、税務署が元本価額で評価して更正処分等を行い、争いになりました。
貸付金債権の評価に関する基本的な枠組みとして、判決は「評価通達による画一評価が原則で、例外は限定的」という考え方を前提にしています。
相続税法第22条の「時価」は、観念的には「客観的交換価値」ですが、貸付金債権は市場価格があるわけではなく、個別に回収率を見積もると恣意が入りやすい、という事情があります。
そのため、財産評価基本通達204は「原則として『元本+利息』で評価する」、財産評価基本通達205は「例外として『回収不能・著しく困難が見込まれる』部分に限って元本価額に算入しない(相続財産から除外してOK)」という構造になっています。
つまり、経営状況が厳しい同族会社への貸付金だからといって、当然に割り引けるわけではありません。
「回収できる見込みが薄い気がする」という程度では、例外(「205」)に乗らず、原則(「204」)どおりの額面ベース評価になりやすい、ということです。
会社にお金がなければ回収が不可能または著しく困難?
まず、本件の出発点(何が起きたか)を、本文から一部引用します。
本件は、被相続人乙(以下「被相続人」という。)を平成27年1月●日に相続(以下「本件相続」という。)した被相続人の子である原告が、被相続人が代表者を務めていた有限会社A(以下「本件会社」という。)に対する被相続人の貸付金債権(以下「本件貸付金債権」という。)について、課税価格の計算の際に計上することなく本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ、新宮税務署長から、本件貸付金債権2205万4347円が本件相続税に係る課税価格に含まれること等を理由として、本件相続税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから、本件各処分が違法である旨主張して、本件更正処分のうち、本件貸付金債権の価額を零円と評価して計算した課税価格及び税額を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
争点はシンプルで、「この貸付金債権の時価はいくらか?」です。
納税者側は、会社が債務超過で損失も続いており、実質的に回収見込みが乏しいのだから時価は零円だ、という主張をしました。
一方、国側は、「204」が原則であり、「205」にいう例外(回収不能・著しく困難)が「客観的に明白」なレベルで認められない限り、元本価額で評価すべきだと主張しました。
そして裁判所は、「205」の「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」を、かなり限定的に解しました。
ポイントは、「『205』の列挙事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白」かどうかです。
本件会社は、相続開始時点で債務超過の状態が続き、経常損失も計上していました。
それでも裁判所は、会社が遊漁船業や旅館業を継続していたこと、金融機関からの借入や返済の滞りが見当たらないこと、貸付金債権に弁済期や利息の定めがないこと、相続の前後で追加の貸付や返済が繰り返されていたこと、などの事情を踏まえ、「経済的破綻が客観的に明白」とまではいえない、と判断しました。
その結果、「205」の例外には当たらず、貸付金債権は「204」の元本価額ベースで評価するのが相当、とされました。
また納税者側は、「実質的に時価が零円のものを額面どおり評価するのは著しく不適当だから、評価通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)に当たる」とも主張しましたが、これも退けられています。
相続税申告で失敗しないためにはどうすればいい?
この判決事例から、相続税申告が必要になりそうな方が特に注意すべき点は、大きく3つあります。
1つ目は、「同族会社への貸付金は、相続財産として見落とされやすい」ということです。
被相続人が社長で、会社の資金繰りを個人が支えていた場合、帳簿上は「役員借入金」「長期借入金」のような形で残っていることがあります。
個人の通帳から会社への入金が続いていても、「立替払い」「生活費のやりくり」の延長の感覚で処理されており、相続人側が「財産」だと認識していないこともあります。
しかし税務上は、形式が貸付金債権であれば、原則として財産計上が必要になります。
2つ目は、「回収困難を理由に評価を下げるには、相当強い客観資料が求められる」ということです。
本件では債務超過や損失の継続があっても足りず、事業継続、金融機関借入の状況、返済の動き、弁済期・利息の設定の有無など、総合的に「破綻が客観的に明白」かが見られました。
言い換えると、「205」を使って元本価額から外したいなら、少なくとも「205」に並ぶレベルの事情、またはそれに近い事情が必要になる、というメッセージです。
3つ目は、「申告からもれた場合、相続税の追加納税だけでなく加算税リスクも現実に発生する」ということです。
本件でも、貸付金債権を計上しない申告を起点に更正処分等が行われ、過少申告加算税も問題になっています。
相続人にとって、貸付金が「返ってこないお金」に見えるほど、申告から外したくなる心理が働きます。
しかし、税務上の評価は気持ちでは動きません。
 想う相続税理士
想う相続税理士