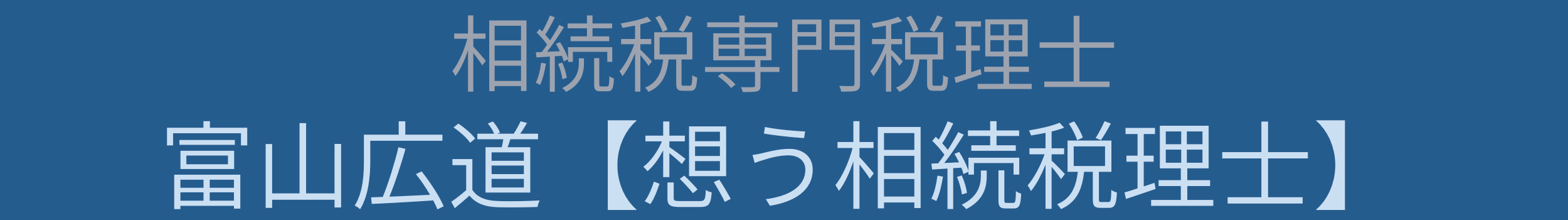相続税専門税理士の富山です。
今回は、評価通達により評価しない「特別の事情」があるかどうかについて争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z268-13120)(一部抜粋加工)
平成30年2月2日判決
相続税評価は「通達」が基本
相続税の土地評価は、原則として財産評価基本通達(評価通達)に沿って行います。
これは、全国で同じルールで評価し、課税の公平性と手続の簡便性を確保するためです。
一方で、実際の土地は千差万別です。
「うちの土地は特殊だから、通達どおりでは実態と合わないのでは?」という疑問が出ることもあります。
このとき問題になるのが、評価通達で「適正な時価」を算定できないような「特別の事情」があるかどうかです。
今回の判決でも、相続人側が複数の土地について、造成の必要性や法規制、がけ地の割合、マンションの特性などを理由に、「通達では時価にならない」と主張しました。
結論としては、多くの主張が退けられています。
通達評価がメチャクチャ不合理だと言えるか?
この事案では、土地ごとに論点が分かれました。
典型的なのは、「造成が必要」「許可が必要」「買主が限られる」といった主張です。
例えば、傾斜地で擁壁工事や盛土が必要な土地について、相続人側は「開発許可の運用上、順次開発しかできないが、通達の補正ではそれが反映されない」と述べました。
しかし裁判所は、実際に一定期間内にエンドユーザー向けに売却され、建物も建築された経過などから、「買主が業者に限られる」という前提自体を認めにくい、と判断しています。
また、市街化調整区域にある雑種地の評価では、「減価率(しんしゃく割合)の根拠がない」と争われました。
これに対し裁判所は、周辺状況(店舗等が成り立つ立地かどうか等)も踏まえ、採用された補正が不合理とはいえない、という整理をしています。
さらにマンションについては、「特異な設計」「専有部分と附属建物を一体処分」「管理費が高額」などが挙げられました。
ただし、管理費等が高いことが直ちに「通達で評価できない特別の事情」になるとはされませんでした。
ここで重要なのは、事情を並べるだけでは足りず、通達評価が「時価とかけ離れる」レベルで不合理になることを、資料で具体的に示す必要がある、という点です。
がけ地はどう扱う?
一般の方が特に戸惑いやすいのが、がけ地(傾斜地)の評価かもしれません。
「土地の半分以上が急斜面で使えないのに、通達で本当に評価できるの?」という感覚は自然です。
この点について裁判所は、評価通達に「がけ地補正」が用意されていること、そして補正の考え方自体に理由があることを述べています。
宅地の一部のがけ地等は、がけ地であることにより、採光、通風等宅地の環境上貢献している効用もあり、がけ地補正率は、これらの点にも着目して定められたものである。
また、がけ地補正と宅地造成費の控除についても、整理もされています。
がけ地補正と宅地造成費の控除とは判断基準を異にするものであることから、両者の重複適用はできないとされている。
実務的には、まず評価通達の枠内で、がけ地補正などの規定が「想定している範囲」に入るかを確認します。
その上で、それでもなお通達評価が著しく不合理だと言えるだけの、客観的な裏付け(取引事例、合理的な鑑定の位置づけ、制限の具体的影響など)を積み上げる必要があります。
「工事が必要そう」「規制があるらしい」という感覚だけで突き進むと、手続きの途中で評価方針が崩れ、申告・遺産分割・納税資金計画まで影響することがあります。
 想う相続税理士
想う相続税理士
ただし、造成・法規制・地形・利用状況など、気になる事情がある土地ほど、先に論点整理をしておくことが大切です。
通達の補正の射程に入るのか、例外として争うだけの材料があるのかで、取るべき手順も、必要な資料も変わります。
早い段階で専門家に相談し、評価の前提がブレない状態で相続手続きを進めることが、結果的にリスクを小さくします。