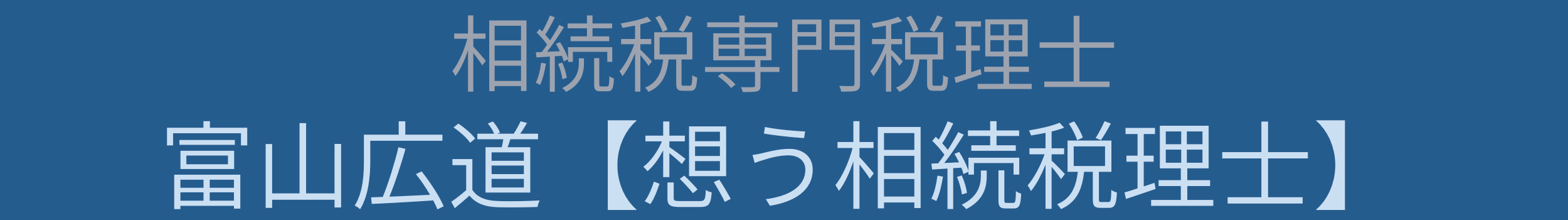相続税専門税理士の富山です。
今回は、裁判上の和解をきっかけに相続税の「更正の請求」ができるのかが争われた判決事例について、お話します。
出典:TAINS(Z267-13097/Z268-13156)(一部抜粋加工)
平成29年12月7日判決/平成30年6月7日判決
相続後に「相続人の口座から亡くなった方の口座への振替」が発覚
本件は、相続税の申告を終えた後になって、相続人名義の信用金庫口座が「本人の知らないところで解約され、被相続人(亡くなった方)名義の口座に振り替えられていた」ことが判明した事案です。
相続人は、信用金庫に対して民事訴訟を提起し、最終的に「解決金」の支払を受ける内容の裁判上の和解が成立しました。
そこで相続人側は、「もともとの相続税申告では、被相続人の預金に本来は相続人の預金が混ざっていた(過大申告だった)」として、相続税の更正の請求(税額を減らす方向の修正)を求めました。
ただし、税務署は「その和解は、国税通則法23条2項1号の要件を満たさない」として、更正すべき理由がない旨の通知を出しました。
この通知の取消しを求めて争いになり、名古屋地裁で棄却等、さらに名古屋高裁でも棄却されて確定しています。
客観的に明確な形で確定されるに至った場合に限る
相続税の更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内(現在は5年以内)など、一定の期間制限があります。
一方で、例外として「判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、計算の基礎となった事実が異なることが確定したとき」は、確定後2か月以内に更正の請求ができる、という枠組みがあります(国税通則法23条2項1号の考え方です)。
本件で争われたのは、裁判上の和解によって「相続税の計算の前提となった事実が、当初申告と違っていた」と言えるほど、客観的に確定したのか、という点でした。
地裁は、国税通則法23条2項1号の更正は、法律関係の安定を崩してでも救済する「例外の中の例外」だと位置づけています。
その上で、和解調書や判決書に表れていない経過資料まで読み込んで、当事者の意図や審理経過から「実はこういう事実が確定したはずだ」と認定していく運用は想定されていない、という線引きを示しました。
法律関係の安定という要請に反してでも救済すべき例外的な場合として通則法23条2項1号が設けられていることに照らせば、同号に基づく更正の請求は、判決等から当初の税額の計算に矛盾抵触があることが客観的に明確な形で確定されるに至った場合に限り許容されるものというべきであって、判決書や和解調書の記載内容を離れて、訴訟の経過を示す関係資料を精査するなどして判決文や和解条項に現れていない審理経過や当事者の意思などを認定し、それを踏まえて更正をするか否かを判断するようなことは、想定されていないと解すべきである。
さらに本件では、和解条項が「解決金180万円を支払う」という形であり、預金払戻請求権の存否や帰属を明確に確定した表現にはなっていませんでした。
そのため裁判所は、「解決金の支払」それ自体から、相続財産の中に相続人の財産が含まれていたこと等を導くことはできない、と判断しています。
以上の観点を踏まえてみると、本件和解において、A信用金庫が180万円を支払うことに合意したのは、飽くまで解決金としての趣旨であって、その金員の法的性格は、本件和解調書上、それ以上に明らかにされていないのであるから、本件和解においては、上記180万円あるいはそれを上回る額の預金払戻請求権を原告甲が有していることが確定したとは認められない。そうである以上、丙の相続財産として申告された財産の中に原告甲の財産が含まれていたこと、あるいは丙が本件口座の解約当時の残高相当額の不当利得返還債務等を原告甲に対して負っていたことが、本件和解の内容から導き出されるとも解し得ない。したがって、申告時において税額計算の基礎とされた事実と異なる事実が本件和解によって確定したとは認められないから、本件和解は、通則法23条2項1号の要件を満たさず、そのことを前提とした本件各通知処分は適法であるというべきである。
高裁も、基本的に地裁の判断枠組みを維持し、「和解調書以外の資料も含めて確定を読み取れる場合まで含む」という解釈は採れない、と述べて棄却しています。
事実認定・確認が、客観的に読み取れる形で書かれているか
相続後に預金トラブルが判明した場合、「税金も修正できるハズだ」と考えたくなる場面は現実に起こり得ます。
ただし、本件が示すとおり、裁判上の和解があったとしても、それが直ちに「相続税の計算の基礎となった事実の確定」になるとは限りません。
ポイントは、和解調書(あるいは判決書)自体に、税額計算の前提を動かすだけの事実認定・確認が、客観的に読み取れる形で書かれているか、です。
実務的には、単なる「解決金」「示談金」の表現にとどまると、税務側は「権利の帰属を確定したものではない」と整理しやすくなります。
また本件では、当初の更正の請求で「評価誤りの額」を180万円として提出した後に、不服申立て段階で約297万円へ拡張しようとした部分が、手続的に不適法と整理されています。
つまり、更正の請求は「出してから広げる」ことが当然にできる制度ではなく、最初の請求の設計が重要になります。
相続の現場では、証拠収集が遅れたり、民事の紛争解決が先行したりして、税務の組み立てが後手に回ることがあります。
そういうときほど、税務側で使う更正の請求の根拠が「どの条文類型なのか」と、「その類型が要求する確定の姿(判決等の中身)」を丁寧に点検することが大切です。
 想う相続税理士
想う相続税理士
特に、国税通則法23条2項1号のような例外ルートは、判決や和解調書そのものから、当初申告と異なる事実が客観的に確定したといえる形になっているかが問われます。
相続税の修正を視野に入れるなら、民事の解決文書の作り方と、税務手続(更正の請求)の最初の設計を、できるだけ早い段階からセットで検討することが重要になります。